2025.06.10
CSR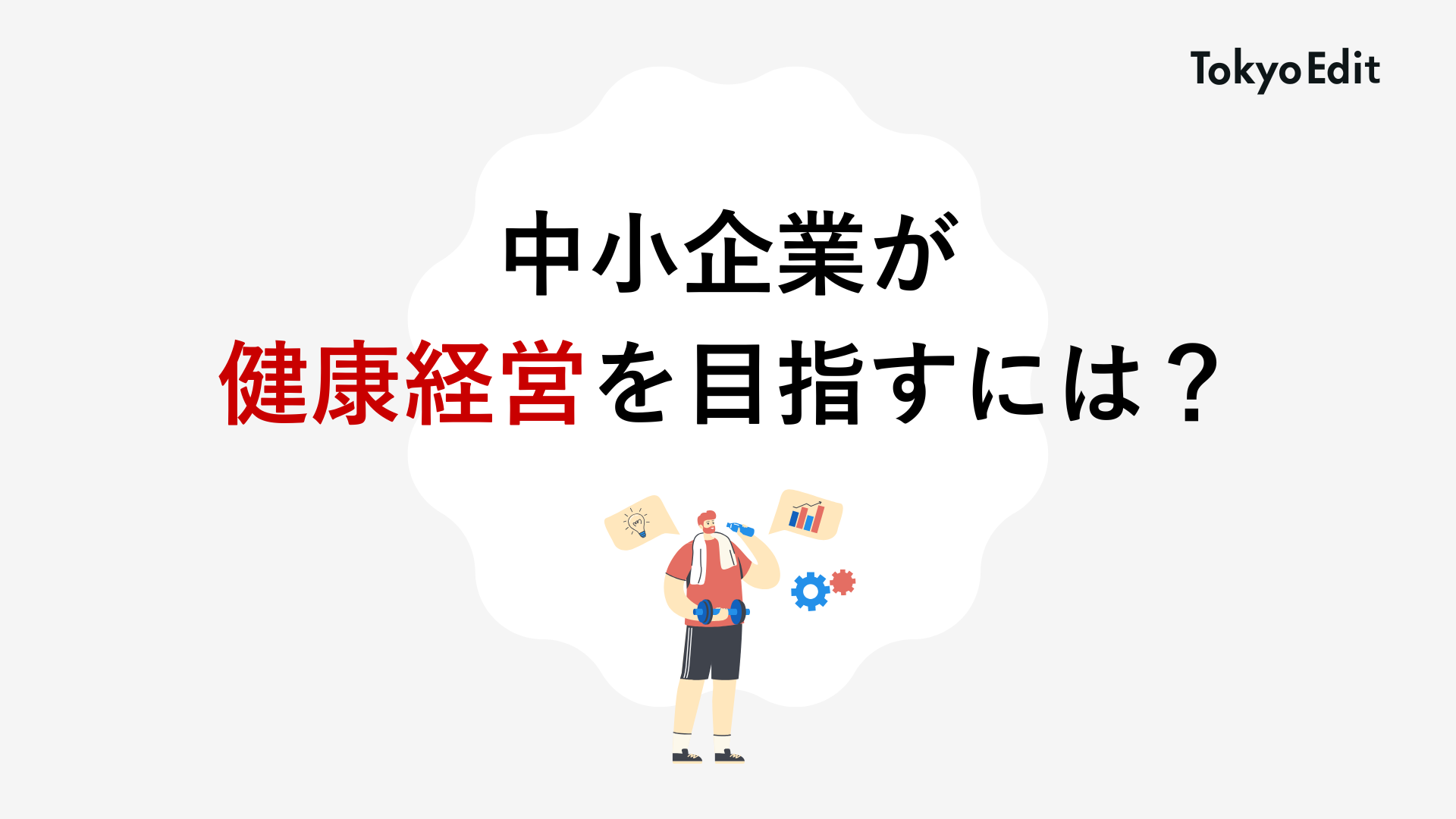
「健康経営が必要なのは大企業だけ」……そう思っていませんか? 人材不足や企業間の競争が激しくなる今、中小企業こそ優先的に健康経営に取り組むべきと言っても過言ではありません。健康優良法人などの認定を取得すれば、企業の社会的信頼性や採用力の向上にもつながります。この記事では、中小企業における健康経営の現状に触れながら障壁になっている課題を洗い出し、中小企業が無理なく健康経営をスタートする方法をご紹介します。
かつては大企業の取り組みと思われていた「健康経営」ですが、いまや中小企業にとっても無関係ではいられません。人材確保の難しさ、従業員の健康不調による生産性の低下、そして国によるさまざまな支援制度──。中小企業こそ、いま真剣に「健康経営」と向き合うべきタイミングが来ています。
健康経営に取り組まない中小企業は、人材確保や定着に苦戦し、生産性の低下や欠勤による業務停滞といったリスクを抱えます。また、企業イメージや信用面で不利になり、助成金や税制優遇といった支援も受けられません。さらには法的責任やCSRへの対応不足といった社会的リスクが発生する可能性もあり、今や健康経営は中小企業にとっても無視できない経営課題となっています。
それにも関わらず、中小企業の健康経営に関する取り組みは大企業に遅れを取っています。厚生労働省と経産省のデータから(2023年時点)、下記のことがわかりました。
ストレスチェックを実施せず、メンタル相談窓口も設けていない企業では、従業員の不調を見逃しやすく、うつ病や休職・退職のリスクが高まります。結果として職場の生産性が低下し、労務トラブルや安全配慮義務違反による訴訟リスクにも発展しかねません。従業員の心の健康を軽視することは、企業の信用や持続可能性にも大きな影響を及ぼします。
中小企業の健康経営が遅れている背景には、構造的・文化的・リソース的な問題が複合的に存在します。
中小企業では、少人数で業務を回しているケースが多く、ひとり当たりの業務負担が大きくなりがちです。そのため、健康経営に取り組むための時間的・人的余裕がなく、「やりたくてもできない」状況にあります。特に専任の人事担当者がいない企業では、総務や経理が他業務と兼務しており、健康施策の企画や実行にまで手が回らないのが実情です。結果として、健康に関する問題が見過ごされやすくなっています。
中小企業では日々の売上や資金繰りが経営の最優先事項となり、「健康施策は余裕ができてから」と後回しにされがちです。また、慢性的な人材不足に悩まされている企業では、「とにかく人を入れること」が先決とされ、職場環境の改善や健康への配慮は二の次になってしまいます。短期的な成果が求められる中で、健康経営のような中長期視点の取り組みは理解を得にくい傾向があります。
健康経営にかかるコストはすぐには業績に反映されにくく、経営者が「費用対効果がわからない」と感じることが多いです。例えば、ストレスチェックや健康指導、産業医との契約などに一定の費用をかけたとしても、それによってどれだけ生産性が向上したかを定量的に示すのは簡単ではありません。明確な数値的根拠が提示できないため、健康施策への投資に慎重になる経営者が少なくありません。
ストレスチェックの結果や健康診断のデータがあっても、それを業務改善や施策につなげる体制が整っていない企業が多く見られます。担当者がデータ分析のスキルを持っていなかったり、ツールやシステムが導入されていなかったりするため、情報が「取りっぱなし」になってしまうのです。データを活用して職場の課題を可視化・改善する仕組みがなければ、健康経営のPDCAが回らず、成果も見えにくくなります。
「健康経営」という言葉は聞いたことがあっても、具体的な内容やメリットを深く理解している中小企業の経営者はまだ多くありません。なかには「健康は自己責任」と考える経営者もいて、企業が積極的に関与すべきという意識が乏しい場合もあります。そのため、施策を提案しても「本当に必要なのか?」という反応が返ってくることが多く、現場主導では進めにくいという構造的な課題があります。
中小企業の多くは、大企業のように専門の調査部門や広報担当を持っていません。そのため、健康経営に関する制度や助成金、成功事例といった情報がそもそも届いていなかったり、探しに行く時間や手段がなかったりします。自治体や厚労省からの情報も基本的には自分から探しにいかなければ得られず、具体的なアクションにつながりにくいのが現状です。結果として「知らなかったからやっていない」というケースが多く発生しています。
健康経営優良法人(中小規模法人部門)の申請には、健康診断の実施率やストレスチェック、労働時間管理、制度の運用状況など、さまざまな項目に対応する必要があります。その内容は詳細にわたり書類も複雑なため、専門知識のない担当者では対応が難しく感じられがちです。特に常に人手が足りない中小企業にとっては、「申請だけで疲弊してしまう」と敬遠される要因になっています。
健康優良法人として認定されても、すぐに業績が伸びたり人材が集まったりするわけではないので、「何が得られるのか分からない」と感じる企業もあるでしょう。たとえ税制優遇や融資の利点があっても、その内容が知られていない、もしくは手続きが煩雑なために活用されないケースもあります。「がんばっても報われないのでは?」という印象が、健康経営へのモチベーションを下げる要因となっています。
中小企業では、非正規雇用や若手社員の短期離職が多く、「どうせすぐ辞めてしまうのだから」という諦めが蔓延していることがあります。そのため、従業員の長期的な健康管理やキャリア形成に投資する意識が育ちにくく、結果的に職場環境の改善や福利厚生の整備が後回しになります。こうした発想のままでは、職場の魅力が上がらず、優秀な人材が定着しないという悪循環が生じてしまいます。
健康経営の第一歩は「現状把握」です。ストレスチェックや生活習慣アンケートを実施することで、従業員が抱える課題を客観的に把握できます。特にストレスチェックは、労働安全衛生法に基づく年1回の義務化対象(従業員50人以上)でもあり、精神的な不調の予兆を早期に捉える手段となります。生活習慣アンケートでは、睡眠・食事・運動など日常の健康意識を把握でき、取り組むべきテーマが見えてきます。匿名で実施することで、本音を引き出しやすくなる点もポイントです。
アンケートに加え、ワークショップ形式で従業員の声を直接聞くことで、よりリアルな課題やニーズを引き出せます。部署や職種を横断して行えば、業務上の健康課題だけでなく、社内の雰囲気や人間関係に関する問題にも気づくきっかけになります。経営層や管理職が参加することで「上層部が健康を大事にしている」というメッセージも伝わり、従業員の信頼感向上につながります。施策の押しつけではなく、共創型の取り組みとして進めることが成功の鍵です。
忙しい中小企業にとって、従業員が業務の合間にリフレッシュできる仕組みづくりは非常に効果的です。出張整体やストレッチサービスの導入は、手軽で続けやすく、業務に支障をきたしにくい方法の一つ。週1回程度の頻度でも、腰痛・肩こり・眼精疲労といった慢性的不調の予防に繋がり、プレゼンティーズム(出社しているがパフォーマンスが下がっている状態)対策として有効です。福利厚生としてのアピールにもなり、採用や定着率向上にも寄与します。
大がかりな制度導入が難しい企業でも、まずは社内掲示やメール、朝礼での一言などを通じて「日々の健康意識」を高めることができます。特に水分補給や姿勢改善は、業務パフォーマンスに直結する要素です。例えば、「1時間に一度立ち上がってストレッチ」「1日1.5Lの水を目安に」といった具体的な行動目標を提示することで、従業員の行動変容を促せます。無理なく実施できる啓発活動は、社内文化として定着しやすいメリットがあります。
ストレスや人間関係の悩みは、業務パフォーマンスや離職の大きな要因になります。そこで外部のカウンセラーやEAP(従業員支援プログラム)と連携し、メンタル相談窓口を設けることが有効です。相談のハードルを下げるために、「匿名OK」「相談内容は秘密厳守」といった運用体制を明確にすることが重要です。社内に話しづらいことでも、外部窓口があれば早期の対処が可能となり、休職やトラブルの予防につながります。
健康経営を「やっている」だけで終わらせず、評価や改善につなげるためには、施策の記録が不可欠です。実施日時・内容・参加者を記録しておくことで、振り返りが可能になり、健康経営優良法人の申請にも活用できます。また、継続的な改善(PDCA)を行う際にも「何が効果的だったか」「どの部署が参加率が高かったか」といった分析ができるようになります。Googleフォームや簡易的なExcel管理でも十分なので、手軽に始めてみるとよいでしょう。
健康経営の成果を見える化するには、満足度調査やストレスチェックのスコア変化など、数値として比較可能な指標を定期的に記録することが重要です。従業員アンケートで「体調が良くなったと感じるか」「働きやすさが増したか」といった定性的な評価と、ストレススコアや欠勤率といった定量的指標を組み合わせると、より説得力のあるレポートが作成できます。こうしたデータは、社内共有や認定申請資料、外部へのPRにも活用可能です。
健康経営の重要性は理解していても、「何から始めればいいのかわからない」「手間やコストが心配」と感じる中小企業は少なくありません。限られた人員・予算でも取り組める方法を知ることで、無理なく、そして着実に第一歩を踏み出すことができます。ここでは、現場の負担を抑えながら健康経営を始めるための実践的なステップをご紹介します。
高木建設株式会社は、地域の他企業3社と合同で「健康研究会」を設立し、健康経営に取り組んでいます。この連携により、禁煙運動を効果的に推進し、2019年には喫煙率を36%から26.6%に低下させました。また、アブセンティーズム(欠勤)の改善にも成功し、生産性の向上を実現しています。
インテリア総合商社の東イン株式会社では、従業員の健康意識向上を目的に、隔週水曜日を「健康推奨日」と定め、従業員が自主的に健康増進活動に取り組む日としています。さらに、従業員の腰痛・肩こり対策として、プロの鍼灸師を招いて施術を行うなど、具体的な健康支援を実施しています。
フィットネススタジオ運営などを手掛ける株式会社アローは、オンライン運動会の開催や健康診断とスポーツイベントの連携など、ユニークな健康経営施策を実施しています。これらの取り組みにより、同社は「健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)」の上位500社として「ブライト500」に認定され、ブランドイメージの向上や健康経営関連の依頼増加といった成果を得ています。
出典:ACTION!健康経営(2025)「認定法人取り組み事例集2025 中小規模法人部門」
健康経営は中小企業でも取り組める、「最も効果的な人的投資」です。大がかりな制度設計をしなくても、「週1回の整体」や「アンケートの可視化」から始めることで、確実に変化が生まれます。今こそ、御社の未来を支える「健康」という資本を見直してみませんか?
OTHERS
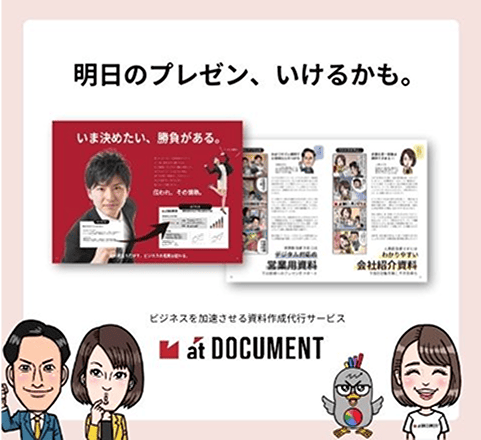

2025.06.11
TECHBubble開発を前提としたデータベース設計のコツ
2025.02.04
NEWSコーポレートサイト開設のお知らせ
2025.06.30
NEWS情報セキュリティ基本方針
Tokyo Edit Tech Blog
開発チームのブログ
Tokyo Edit CSR Blog
CSR活動に関するブログ
OTHERS
